何故か三浦半島だけがロボットが自動車を運転しても良い地域に指定されていた為に、シンジの見舞いに訪れその余りにもな容態に驚いた加治首相からシンジの療養中の手助けをするように言いつけられたセリオは1週間が経過し落ち着いた事から、シンジ達(主に看病疲れのアスカ達に対して)の気分転換に日帰りで出掛けようとアスカ達に提案したのだ。
Gアイランドの地下病院から海底通路を抜けて川崎に出た3人と1体は横須賀線に乗って三浦半島の付け根、鎌倉へとやって来た。
そこでレンタカーを借りたセリオは未だに半覚醒の状態のシンジを車椅子ごとワンボックスカーに乗せて三浦半島へドライブに出た。
何故か、首都圏とは思えないほど寂れている三浦半島の様子に疑問を持ちながらも、妙に心落ち着く風景を見ながらセリオの運転するワンボックスカーは朝比奈峠を越えて岬を目指した。
「−−少し道が悪いので揺れますが、お二人とも大丈夫ですか?」
セリオは後部座席に座ってシンジを両側で支えているアスカとレイに声を掛けた。
「大丈夫よ。でも出来るだけ静かに頼むわね」
「−−ハイ、アスカさん」
そう言うとセリオは先ほどよりも気合いを入れて道路の状態をチェックし始めた。
そんな様子を見て「まったく真面目なんだからセリオは」とアスカは苦笑を漏らした。
だが実際の所、アスファルトの道路はまるで数十年間も放置されていたかの様であり、路面の状態としては酷く悪かった。
さて、今回セリオが提案したドライブの第一の行き先は時空転移の際のポテンシャルの差異からか半島の南側に傾斜しながら約10メートルほど水没した半島の南端から見える相模灘の絶景だった。
彼女が利用している来栖川のサテライトサービスで一時期話題になった場所であり、彼女自身が一度行ってみたい場所のひとつとしてキープしていたところでもある。
セリオの姉妹のひとりが上げていたポートレイトに写された、その写真は何故か開放感を感じさせる物があったのだ。そして、今のシンジにとってそう言う景色などを見せることで意識が回復する可能性が高いと主治医の意見もあり、こうして外出の許可も下りたのである。
元々、世紀末の時点に於いても人家のまばらな地域であったのだが、現在の風景はそれに輪を掛けて閑散としていた。
現在の三浦半島は先端の横須賀港こそ無事であった物の、その南側はほぼ海中に没していた。
だが、それによって死者が発生した訳ではなかった。
三浦半島の南側は温室効果による高潮によって元々海面の上昇が始まっていた世界だった為だ。その為かどうか、人口の激減したその世界では物の流通も低下し、世界は黄昏の時代を生きていたという。
その為にであろうが、滅多に人の来ないこの地に限らず全ての物は朽ちて行くまま新たな手を入れられる事は滅多にないようだった。
その様な道を進まなければならなかったセリオは慎重に運転した結果その目的地、件のセリオがポートレイトを撮った場所を見つけワンボックスカーを駐車させた。
そこは山の山腹の少し膨らんだ様な休憩所のような駐車場だった。
セリオが慎重にシンジの車椅子を下ろし、アスカ達もそれを手伝った。
ガラガラと音を立てて手摺りのある展望の良い場所へ車椅子を押して行くと、そこには広々と広がった相模灘が凄いパノラマで広がっていた。
夏の陽気の所為かガスがかっていたが、遙かに広がる大海原の向こうには微かに房総半島の低い陸地が見え隠れしていた。
青々とした海原には、最近交流が活発になりだした中華共同体との交易船が行き交いし、太陽の照り返しが映り込みキラキラと輝いていた。
アスカ達もその風景を見て少し衝撃を受けていた。
別に景色の良さに、ではない。
彼女たちの足元、海岸から少し海に入ったところ、そこに彼女たちにはお馴染みの、彼女たちが育ってきた世界では極ありふれた景観が再現されていたからだ。
山裾を辿って落ちたその先、海中から顔を覗かせていたのは海没した都市の名残であるビルディングである。
セリオは知らなかったが、アスカ達の来た世界ではセカンドインパクトと呼ばれるカタストロフによって南極の氷が溶け海水面が20メートル近く上昇し、世界の軒並みの都市が水没していた。
その為、アスカ達にとって海とはビルの生えた景色が当然であり、この世界に来てから体験した砂浜の方が異質な存在だったのである。
しかし、ここから見える景色は彼女たちの世界その物であった。
三浦半島の南端、城ヶ島を望む位置にあった三浦市が海の底に沈んでいたのだ。
少し空気が冷えてきた頃、セリオの運転するワンボックスカーは半島の西側を北に向かって進んでいた。
あの景色を見てもシンジはボーっとしたまま、こっちの世界に意識を戻しては来なかった。
ガッタンゴットンと揺れる細い道を車は行く。
元々は別荘街があったらしい草地の真ん中に延びる細い道をゆっくりと走っていた。
「シンジ、何も反応しなかったわね」
「ええ」
「あの景色、私達のいた世界に良く似ていたから、もしやって思ったんだけどね・・・」
「そうね」
「もしかして、シンジ・・・ずっとこのままなんじゃ」
「そんな事無いわ」
「! どうしてそう言えるのよ」
「だって、シンジくんは私達を守ってくれるって言ったもの。必ず戻ってくるわ」
「! ・・・・・・そうよね。どのみち、私達には出来ることをするしか無いんだわ」
「大丈夫よ、アスカ。シンジくんは私達を守るために疲れすぎたの・・・疲れが癒えたら必ず戻ってくるもの。きっと大丈夫よ」
アスカを励ますような言葉を紡ぐレイだったが、その実、その言葉はレイ自身に向けられていたのかも知れない。
その言葉が出されると暫く言葉が途切れた。
何処までも続くようなススキの原が不意に途切れた。
「−−あ」
セリオは正面に見えた建物に気付くとワンボックスカーのスピードを落とした。
「なに? どうしたの?」
アスカは突然のセリオの行動に疑問を持ったらしく、前席のセリオに声を掛けた。
「−−あ、いえ。現在時刻15:00ですので、午後のお茶にしませんか?」
「午後のお茶って言ってもこんな辺鄙なところで?」
それを聞いたセリオは正面に建つ昔の米軍住宅風の白ペンキの家を指さした。
アスカはまだ少し離れたその建屋の脇に小さく下げられた看板を見る為に目を凝らした。
「えーと。Cafe’ Alpha. open.本当、確かに喫茶店ね。こんな所に」
「−−どうします?」
重ねてセリオが訊いてくるが
「いいわね。入りましょ」
アスカが同意するとセリオはカフェアルファへ続く道へとハンドルを切った。
セリオが運転するワンボックスカーは草だらけの駐車場に静かに停止するとエンジンを切った。
アスカとレイがシンジの座った車椅子を協力して一緒に下ろそうとすると、運転席にいたセリオが声を掛けてきた。
「−−アスカさん、レイさん、少々待って下さいませんか」
「何?」
直ぐにでも車椅子を押して行きたかったアスカは呼び止めたセリオに不機嫌そうな顔を向けた。
「−−申し訳有りませんが、少し車外で待っていて下さい」
「だから何でよ」
何かはぐらかすようなセリオの態度にカチンと来たアスカは彼女に詰め寄った。
「−−・・・シンジさんのオムツを交換してから行きたいと思います。これはシンジさんのプライバシーを守るため及び衛生的に必要不可欠と思われますので」
セリオは淡々と説明を始めたが、自分が誤解していたこととシンジのオムツを替えるシーンが脳裏に浮かんできてしまったため慌てて頭を振ってセリオの言葉を遮った。
「セ、セリオもう良いから分かったから! じゃあ外で待ってるからね」
「−−はい、申し訳御座いません。手早く済ませますので。・・・・・・覗いてはいけませんよ」
「! そ、そんな事する訳ないでしょう! 何言ってんのよ! バッカじゃないの!」
顔を真っ赤に染めたアスカは肩を怒らせながら車から少し離れたところへ足音も高く歩いていった。
数分後、奇麗に身支度を整えられたシンジは車椅子ごと地面に下ろされた。
そして3名はセリオが車内の換気を済まして異臭が無くなったことを確認してから出てくるのを待って喫茶店へ向かった。
その店は進駐軍のアメリカ軍邸宅を思わせる色合いと造りで、白ペンキに塗られた母屋の脇に僅かに設けられたスペースに建てられていた。
店内は外観から推測するとかなり狭そうだったが4名位なら問題はなく入れそうだった。他に客のいる様子もなかったし。
何でも一番! が好きな(条件付けられていた)アスカは先頭に立ってその扉を開け放った。
彼女が中にはいると店内には緑色の髪をした女性と紫掛かった茶色の髪をした女性が「如何にも喫茶店です」と云った格好をし、上気した顔で勢い良く挨拶した。
「「いらっしゃいませっっ!!」」
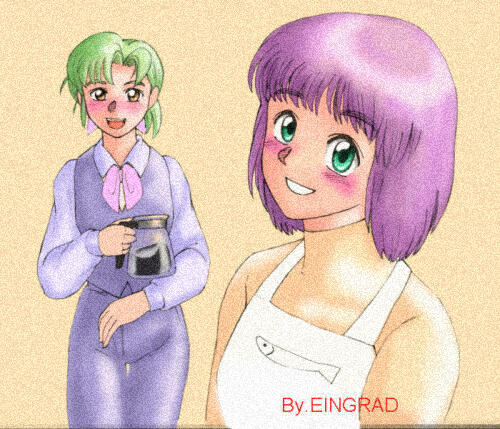
ちょっと気合いの入った挨拶にアスカは戸惑ったが、外見上は何事もなかったかの様に振る舞い店内に入った。
「こんにちは。4名ね。ひとりは車椅子だけどいいかしら」
「あ、はい。いま椅子どけて場所作りますね」
そう言うとカウンターにいた蝶ネクタイ(みたいなリボン?)を締めた女性が机の用意をしようとしたが、もうひとりのエプロンを掛けたウェイトレス(ちなみに紫掛かった髪の女性)がそれを押し止めた。
「あ、こっちは私がしますから アルファさんは用意の方をお願いします」
「あー 悪いねココネ」
てへへと笑うアルファだったが、ココネと呼ばれた方はそれを良しとしなかったようだ。
「もう アルファさん。わたしの方がご厄介になってるんですから それくらいさせて下さい」
「うーん ま そうだねー。 すぐ済みますからーちょっと待ってて下さいね。あ、おふたりは奥の方へどうぞ」
アルファはふたり掛けの席の奥側を勧めた。
なにしろこの店内は狭い。
ふたり掛けの机がふたつしかなく、カウンターの他にはベランダに机がふたつあるだけなのだ。
もっとも、いままではこれでも充分すぎるほどだったのだが。
彼女たちの来た世界は地球温暖化により海面が上昇、科学技術は飛躍的に伸びていたのだが、科学の進歩に対する疲れもあったのだろうか世界の人々は黄昏のような穏やかな衰退の時代を生きていたからだ。
その為、ここさがみの国三浦半島は首都圏内であるにもかかわらずほとんど人の通わぬ僻地と化していたからだ。
セリオは椅子を片付けた手前の席、ちゃんと直射日光を避けるようにしてある席に車椅子ごとシンジを座らせた。
そこから見える景色はなかなかの物であったが、それでもシンジは相変わらず焦点を結ばない視線を投げかけているだけだった。
「はい、これメニューです。ご免なさい、品数少ないですけど」
ココネが椅子を母屋の方へ持って行っている間にアルファは各テーブルにメニューを差し出した。 が、セリオは申し訳なさそうな顔をして頭を下げた。
「−−大変済みませんです」
「え? なにか ありました?」
「−−いえ、申し遅れましたが私はロボットですので・・」
そう言うとセリオは頭部側面に装着したサテライトシステム対応のイヤーガードを指さした。 しかし、アルファはそれを見てもロボット風情が、等と顔を顰めることもなくにこやかに笑みを返した。
「あ、そうなんだ。で、ブレンドでいいですか?」
「−−いえ、ですから・・・もしよろしければ、できればコンセントをお借りしたいのですが」
「コンセント? 別に構いませんけど 何か充電するような物でもあるんですか?」
アルファはセリオの質問に首を傾げた。
「−−いえ、ですから私の畜電池に充電をと思いましたので」
「はぁ、だったら机の下のコンセント 使っていいですよ」
彼女は何か釈然と無いまま机の下のコンセントを示した。
「−−ご厚意大変にありがとう御座います」
許可を貰ったセリオは深々と頭を下げた。
「ねぇ、このメイポロってなに?」
さっきからメニューと睨めっこしていたアスカが先程から気になっていた一品の事を聞いてみた。
「あ、はい。 それはそういう木の汁のお湯割りなの。それにする?」
「うーん、じゃあそれにするわ。レイはどうする?」
「・・・紅茶はないのね。・・・このソバ茶でお願い」
「はーい。じゃあメイポロとソバ茶ですね。彼は?」
アルファは無反応なシンジの注文を聞いてみた。
「−−シンジさんの栄養補給は主治医の指示により1時間前に済んでいますので、相済みませんが」
セリオは並列充電をしながらアルファに答えた。
「うーん それは残念」
そう言うと彼女はカウンターへ戻った。
そこへ母屋から帰ってきたココネがお冷やをお盆に乗せて最初はアスカとレイのテーブルへ。
「はい、お冷やですどうぞ」
「ありがとう」
「はい、どうぞ」
「ありがとう」
次にセリオ達の席に向かったココネは、びっくりした。
「わっ!」
「−−どうかなさいましたか? ああ、これに驚かれてしまいましたか」
そういって彼女は手首から延びたケーブルを撫でた。
「−−なにも知らない方にはショックですね。驚かせてしまい大変に申し訳ございません。直ぐに外しますので」
セリオは直ぐにコンセントに繋がるコネクターを外そうとしたがココネは慌ててそれを押し止めた。
「い、いえ。そのままでいいです。こちらこそ、人のプライバシーを傷つけることをしてしまって ゴメンなさい」
「−−? いえ、わたしはロボットですから 人間の方の精神に対して危害を加えてしまったことに対し謝罪しなくてはなりません。ですが、現在、蓄電池の容量がエンプティーの為、ご厚意をありがたく頂き充電を進めたいと思います」
「でも・・・」
「−−私のような物に対して重ね重ねご配慮ありがとうございます。ですが、私はメイドロボに過ぎません。お気になさらないで下さい」
セリオの慇懃無礼とも言える態度に気圧されたココネは一応お冷やを彼女とシンジの前に置いた。
アルファの店では冷たい井戸水を汲み置きして、それに火を掛ける所から始めるので少し時間が掛かったが、10分後には注文の品が上がった。
縦長のガラスのマグに入ったメイポロはアスカの前に、丸いガラスの湯呑みに入ったソバ茶はレイの前に置かれた。
「あ、そうだ! ちょっと待っててくださいね」
そう言うとアルファは急ぎ足で母屋に駆けていったかと思うと、直ぐに戻ってきた。
「はいどうぞ。この前ヨコハマ見物に行った時買ってきた月餅なんですけど」
「え、でも頼んでないけど」
「えへへ サービスで いやー この店辺鄙なところにあるでしょ? 滅多にお客さんが来ないから嬉しくって」
そう言うとアスカの返事も聞かずにカウンターに戻ってしまった。
しばし、静かな空気が流れた。
アルファ達のいた世界に流れていた空気か、非常に穏やかな雰囲気が流れていた。
と、突然「あ、そうだ!」とばかりにアルファは人差し指を立てた。
アスカ達一行がそんな彼女に注目するとアルファは照れたように後ろ頭に手を当てながら壁に立てかけてある楽器を手に取った。
「じゃん!」
彼女はその楽器を見せびらかすようにして、帯を首に掛けた。
「本当はこんなに大勢の人の前で弾いたりはしないんだけど、彼、シンジさんの為に弾きます」 ピックを摘み、丸い胴体をしたその楽器の弦に当てた。「これは私のオーナーの好きな中国の楽器で月琴て言うの 正式な弾き方じゃないんだけど」
そう言うと彼女は流れるような旋律を紡ぎだした。
アルファが月琴を弾くと店内に不思議な雰囲気が漂った。
それは決して不快な物ではなく、誰もが一度は感動したような光景を思い出すような気分にさせられた。
ふと気付くと、傍らに座っていたココネがその旋律に乗せるようにハミングをしていた。
曲はつぎつぎと移り変わり、月琴の音色とココネ、アルファのハミングが合わさりその大きなうねりに皆の心は引き込まれていた。
最後に残った弦の響きが消えた瞬間、それを聞いていた全員が「ほぅ」と息を吐いた。
「・・・スゴイ・・・って言うか・・・、アタシは今まで情操教育って事で歴史上の名演奏者達の演奏記録を聞いてきたけど・・・こんなに引き込まれたのは初めて・・・」
「−−私も、感動と言える情動を記録しています。先程までの感覚を記憶装置に書き込もうとしていますがメモリーがオーバーフローして今ではその輪郭しか思い出せません」
「レイ、アナタも感じたでしょ。今の、音楽。私は日本語ではスゴイ、としか表現できないけど」
「ええ、それよりも・・・」
「なに? どうかしたの?」
アスカはレイが何か別の物に関心を引かれていることに気付いた。
あれほどの感動の余韻の中で、自分はなにも考えられなくなっているというのに。
そんなレイの冷静な精神に驚くと共に、その対象が何なのか俄然興味が湧いてきてしまった。
アスカがレイの視線を辿ってみると・・・。
レイが注目していたのは、シンジの指先だった。
相変わらずシンジの顔には何の変化も表れてはいなかったが、彼の左手はまるでアルファの月琴に合わせるように、指先を動かしていた。
それはあの事件以来、シンジがエヴァからサルベージされて以来、初めて見る自発的な行動だったのだ。
「! シンジ!」
思わず我を忘れてアスカはシンジに駆け寄った。
暫くシンジは指を動かしていたが、その内にそれも止まり、元の様子に戻ってしまった。
まるで、魂がきちんと体に被さっていないかの様な印象を受ける。
レイはそんなシンジの様子から、昔、第三使徒が第3新東京市に襲来する以前に赤木リツコ博士から渡された碇シンジについての調査報告書のことを思い出していた。
「昔、シンジくんの身上書を見たことがあるわ。確か、チェロを小さい頃から習っていたって。あの動作は弦楽器の演奏パターンに近いもの。きっとそう」
「−−チェロですか・・・」
少し考え込んだセリオだったが、あることを思いついた。
「−−すいません、ちょっと訊いてきますのでシンジさんをお願いします」
「ええ、構わないわ」
セリオはそう言うと喫茶店のドアーを開けて、ベランダに出た。
彼女は中空に目を向けると、そのままの姿勢で固まってしまったかの様に身動きを止めてしまった。
窓からその様子を見ていたアスカは最後に会話を交わしたレイに聞いた。
「セリオなんだって?」
「聞いて来るって・・・」
「訊くって一体なにを?」
「私知らない。聞かなかったもの」
「だぁーっそれじゃ何の意味もないじゃない。肝心要なのはそれでしょうが」
「そう? ゴメンナサイ、アスカ」
「う、」もしかしてアタシ言い過ぎだった?「わ、分かれば良し。次からは気を付けてよね」
「ええ、分かったわ」
そんなこんなしていると表に出ていたセリオが戻ってきた。
「−−お待たせいたしました。この近くにPHSの端末がなかったものですから、高出力の衛星通信を行っていたのですが・・電波障害などは発生しませんでしたか? 一応、影響を考慮して通信を行ったのですが」
「へ? アンタそんな事まで出来るわけ?」
「−−ハイ。来栖川電工が開発したHM−13シリーズには標準でサテライトサービスが付属していますので電波状態が良ければ地球上の如何なる場所からでも来栖川のスーパーデーターベースに接続が可能。と言うのがセールスポイントでしたから。ただ、現在の所、静止衛星軌道の使用が非常に難しいため、数少ない低軌道衛星を用いるしかなく、食の時間が多いのが現在の所ネックとなっております。しかし、その分出力の低減が可能になりましたのでより長時間の通信が可能となっております。何れにしても痛し痒しでしょうか」
「企業CMはいいんだけど、で? セリオ、アンタは一体何処に何を通信してた訳? 勿論教えて貰えるんでしょうけど」
「−−はい。私の所属機関を通して加治首相に・・・・お強請りを打診しておりました」
「おねだり?」
「−−はい。シンジさんはチェロを欲しているようでしたので、出来るだけ迅速にチェロを搬送できないか、と訊いたのですが」
「それで?」
「−−残念ながら今すぐここに運ぶことは不可能との事でした」
それを聞いたアスカは頭を垂れた。
「ちぇー、期待して損しちゃった」
「−−ですが、加治首相からの伝言がありまして」
「伝言? 一国の首相がわざわざ?」
加治首相などというトップレベルの名前がさらっと出てきた為、アスカは驚きに目を見張った。
アスカがネルフにいた頃は「たかだか」日本の首相という認識しかなかった日本の最高権力者である首相であったが、この世界に来てその辣腕を持って混乱した日本をまとめ上げただけでなく、今まで交渉のなかった諸外国との交渉を成功させた凄腕の政治家である加治首相にはさしものアスカも一目置いていた。
確かに、シンジのサルベージの時に最も危険な場所であるGアイランドへ僅かな人数だけで乗り込んで来た上、シンジを見守ってくれていたと後に大河長官に聞いた時には驚いたし、その後シンジの看護のためにセリオまで付けてくれただけでも感謝なのに。
「で、内容は何なの」
「−−はい、要約しますと。<シンジくんの快復のきっかけが掴めるなら、私達は全面的にバックアップする。少し早めの夏休みを過ごしてくれ給え>以上です」
「ふぅ〜ん。向こう持ちで?」
「−−はい。政府の厚生費で落とすには問題があるとのことでしたので、加治首相のポケットマネーから出される様です」
「へーっ、流石太っ腹ねぇ。・・・・そんなにお金持ちなの?」
「−−と言うよりも、公務で忙しい方ですし、ご家族の方々とは生き別れ。私を購入した費用で少しは目減りしたでしょうがそれでも自由になる資産にはまだまだ余裕があると思われますが。それに、あの方があなた方のことを知ってからは常にあなた方のことを思い悩んでおいでの様でした。それからするとあなた方のために少々骨を折ることが出来るのは却ってあの方の心労を減らすことになると思われます。是非とも提案に乗っていただきたいところですが。構いませんでしょうか」
まぁ、世界最強のエヴァンを操ることが出来るチルドレンたるこの私達のことが気になるのは当然だから感謝する言われもないんだけど
「そうね。じゃあそうさせて貰うわ。レイも構わないでしょ」
「賛成する理由はあるけど拒否する理由はないわ」
「じゃあそう言うことで。よろしく頼むわ、セリオ」
「−−ハイ、了承しました。では逗子市に宿を取り、また明日こちらへ観光に参りましょう」
「Gアイランドへ戻らないの?」
「−−ハイ、残念ながらロボットの私が公道上での自動車の運転などが許可されていますのは、逗子市・葉山町・三浦市・そして横須賀市の西半分の<さがみの国特別自治区>の中だけですので。移動の利便性を考えますとこの特別区域を外れますのは大変不利だと思われます」
「な〜るほどね。そう言うことなら納得できるわ。・・・・でも、何でこの自治区だけロボットの、その、自律行動というか、責任制度というか、・・・認められているわけ?」
「−−はい、それはですね・・・」 −検索中− 「自意識を確立した自律人工知能の開発に成功したこの世界のロボットが存在することを鑑み、この地区の有力者である初瀬野と言う方が提唱した法案が可決された、と記録にはあります」
「へー、でもそれらしいロボットどころかそんなにスゴく科学が進んだ世界には思えないけど」
アスカはここへ来るまでに見た閑散とした風景を思い浮かべ、それと完全自律人工知能と云う非常に達成が難しい技術とはどうしても結びつかず頭を捻った。
「あ、皆さん。これからちょっとしたイベントが有るんでベランダに出てみませんか?」
それまでニコニコと微笑みを浮かべていたアルファが唐突に提案した。
アスカが彼女に振り返ると、アルファとココネは自分用のカップと、ポットに入れたコーヒーを持ってドアーの前に立っていた。
「へ?」
アスカが気の抜けた疑問符を漏らすと、アルファは「ふふ」と微笑みを浮かべた。
先ほどの月琴とのコーラスと言い、何かと驚くことの多いこのふたりの喫茶店勤務の女性達のすることに興味を覚えたアスカは二つ返事でOKを返した。
「で、一体どういったイベントな訳!?」
勢いこんで聞いてくるアスカであったが、アルファははこう返した。
「うふふ、結構驚くかも知れませんよ」
と言うワケで話に乗った皆はアルファの提案を聞き夕日が当たるベランダに出た。
「それじゃそこの椅子にでも座って待ってて。いまコーヒーカップ持ってくるから」
そう言うとアルファは店内に取って返すとアスカとレイの分の2脚コーヒーカップを持って出てきた。
それをアスカとレイの前の丸テーブルの上に並べると、淹れ立てのコーヒーを注いだ。
「これはサービスで、今日は珍しく沢山のお客さんが来てくれて本当に楽しかったから・・・」
「ふ〜ん。これで忙しいなんてよっぽど寂れてるのね」
「えへへ」
コーヒーと会話を楽しみながら、その十数分後。
「うーん、もうちょっと掛かるのかな? 」
アルファは西の空の方を眺めながら呟いた。
「一体何があるの?」
「それは見てのお楽しみって事で」
・
・
・
・
「あ、来た来た!」
アルファが歓声を上げるとシンジを除いた全員が空を見たが、まだまだ蒼かったが赤く染まり始めた空には厚い大気を通ってオレンジ色に染まり始めた雲が見えるだけだった。
「え? 何が見えるのよ。・・・・むぅ、何よ何も見えないじゃないの。レイは見えた?」
「いいえ、特に異常は見当たらないわ」
「そうよね。セリオは?」
「−−私のセンサーにも特に変わったファクターは検出されておりません。何かの見間違いではないかと・・・」
セリオまでがそう言うとアスカはアルファに聞き返した。
「一体何が見えるってのよ。何も見えないじゃないの」
「あ、やっぱり分かりません? 私も初めて見たときはそうだったんですよ」
「??? 本当に見えてるわけ?」
「もちろん。多分見え過ぎて良く分からないんだと思うよ」
「で、一体何が見えているってのよ。ヒントぐらいくれてもいいじゃない」
「あー、まぁー。つまり、飛行機なんだけど」
「飛行機?」
それを聞くとアスカは首を後ろに倒して周囲の空を捜索してみた、だが、やっぱり分からない。
「いないじゃない。そうか、音が聞こえないって事は高空って事ね。今どの辺にいるわけ?」
「えーっと、丁度月の側かな?」
「月? うーんと」
するとアスカはどんな小さな点も逃さないように目を凝らして高空にいるであろう航空機の輝点とその後ろの飛行機雲を捜した。
しかし、そこにはゆっくりと移動する白い雲があるだけで、彼女の知るような範囲の航空機の特徴を持つ移動物体の姿は掴めなかった。
そう、普通の索敵ならばそれが最も確実な方法なのだが、人間、自分の常識を凌駕する物を目撃した場合、例えそれが完全に視界に入っていたとしてもそれを意識が認識することが出来ないと言う事が存在する。
丁度今のアスカがそのいい例だった。
「すごーく、上よ。で、かなり大きいから」
「・・・・・・・・・・・・アスカ・・・・・・・・」
「何? レイには分かったの?」
「ええ・・・、・・・・あんなもの見たこと無いわ・・・・・・」
レイはそう言いながらボーっとした顔で上空を惚けたように眺めていた。
「すごい・・・? おおきい・・・」
唇を尖らせて首を傾げたアスカは少し気を抜いて今まで狭い範囲に集中していた視界を広い範囲に広げてみた。
するとそれまでその構造物の一部しか見ずに無視していた存在が目に入った。
「は!?」
思わず目を疑ったアスカは閉じた瞼を腕で必死に擦って、再度それを見た。
それまで白い雲だとばかり思っていたそれだったが、よくよく考えてみると1万メートルを超える高空に雲が掛かるなんて事はなく、ましてやそれが目に見える速度で移動するなんて事がある筈がなかったのだ。
「な、な、な、・・・・・・なによアレーッッッッ!!!!!!」
完全にそれを認識したアスカは大声で絶叫してしまった。
「えーっと、確か名前は「ターポン」って言って。スゴイ高いところを飛んでいる飛行機なんだって。一応人が乗っているって聞いたけど、もう何十年も飛び続けていてもう降りられないとか聞いたわ」
「でしょうねー」
それを聞いたアスカは大体そのターポンという飛行機についての性能を把握してしまっていた。
恐らく主動力は何らかの形で太陽エネルギーを吸収し推進力に変換するシステムで、大気圏上層部、と言うより宇宙空間と呼んだ方が相応しい高度をほぼ衛星速度で進みながら中間圏上層の薄い大気を機体下部にぶつけ、その衝撃波に波乗りするような形で進む大気層水切り効果を利用した、亜スペースプレーンである事。
そして、目視から推測した機体の大きさは全長10キロと言うバケモノじみた機体、そしてそれが故に成層圏より下の濃すぎる大気の中を飛ぶことは出来ず、二度と大地に着陸することは不可能であろう。
その上に、その高度をそのスピードで進む航空機に対して空中ドッキングする事すら不可能、つまり有人機であると言う事だったから、乗っている人間たちはもう二度と地上に足を降ろすことは出来ないと言うことまで理解してしまった。
ボーゼンとそれを見送った一同だったが、東の空へ霞むように飛び去るとほうっと一息ついた。
「どうです? すごいでしょ。 私もずーっと頭の上を飛んでいたのに数十年間も気付かなくて、教えて貰ってから初めて気付いたの。 あんな風に空の天井に描かれたみたいに見える物が人が作った道具だなんて信じられないですよね」
アルファは少し興奮気味な声でアスカに言った。
アスカも黙って肯きそれに同意したが、この世界に来てから常識外れの物ばかり見てきているため動転して何も手に着かない、と言うほどの物でもなかった。
それよりも大切なのは、彼女たちのコンサートと云うかセッションにシンジが反応したと言うことだった。
シンジの意識が戻ってきていない事が判明してから、GGGや加治首相を初めとする大人達は藁にもすがる思いで様々な分野の達人達に声を掛け、少しでも早くシンジが元に戻るように治療方法を調査しようとしていたのだがそうして訪れた者達の中には真っ当な科学者と言うよりも闇のサイボーグ技師や錬金術師みたいな者もいた。
現代医学の権威達は離人症の一種か脳神経に過負荷が掛かった所為であると診断していたが積極的な治療法はなく対症療法での長期治療しかないと結論をしていた。
アスカは例の怪しい風体の中にひとり気になることを言っていた男が居たのを思いだしていた。
その男は自称「ヨーロッパの魔王」とか言う老人で、言葉遣いが辿々しい女性型アンドロイドを連れていたのだが、彼はシンジの側に寄るなりゴーグルのような物を目に当てるとひとつ肯いてこう言った。
「ふむ、新しく作られた体にまだ魂が馴染んでいない様じゃな。なに大丈夫、これじゃったらこの少年が興味を引くことをしていればその内にこの体が自分自身の物だと認識できるじゃろうて。それよりもしっかり霊体が固定される前に浮遊霊にでも乗っ取られることの方が心配じゃな・・・どうじゃ!? ここは儂の特製のお札を身につけていれば心配無用なんじゃがの」
そういって実に怪しげなお札を懐から取り出したこの老人は皆の反感を買い結果的に無視されてしまったのだが、特にこういったオカルトなぞ信じていなかったアスカは無視出来ずに食ってかかっていった。
「なにアンタ!? こんなシンジを餌にして似非霊感商法で儲けようって云う魂胆な訳!? ふざけないでよ!!」
老人はそのアスカの剣幕にタジタジとなったが、先ほどのゴーグルを取り出すとアスカの目に押し当てた。
直ぐにそれを引き剥がそうとしたアスカだったが、そこに見える映像に唖然とした。
「なに? 合成なの?」
「どうじゃな嬢や、坊主の上にもうひとつ坊主が見えるじゃろうが。どうやら霊体の紐はくっついているようじゃが慣れない体に戸惑っている様じゃな。坊主が気に掛けている者がいればその内にどうにかなるから心配せんでも良い」
アスカが見た映像は俗に言うキルリアン放射を写真に撮った様な感じで体を取り巻く光に阻まれてその上に浮いているシンジが弾かれていると云ったものだった。
又この老人の云っていた事の中に誰にも知らせていない一辺の真実が有った事に気付いた。
何故この老人はシンジの体が新しい物だと断定したのか。
確かに、エヴァ初号機から得られた映像で元々のシンジの体がエントリープラグの中に細胞単位で分解されて行く様子が写されており、戦いの後に初号機のコアからシンジの体が「発生した」記録があることから、このシンジが本物かどうかの結論もまだ出ていなかったのだ。
それは完全に秘密であったはずなのだが、この老人はそれをあっさりと看破した。
絶対にオカルトなんて信じるつもりの無かったアスカであったが、「溺れる者は〜」の諺にもあるように今はどんな真実の一辺でも実効性があるならばと神頼み的なそのお札を無意識の内に購入してしまっていたアスカであった。
結局の所それが役に立っている様子はなかったが、何か悪いことをしている様子もなかったため未だに鞄の片隅に忍ばせていたのである。
後にエヴァとGS達の技術が発祥となって神秘学が発達した後もそれらを撥ね除けていたアスカの、その長い生涯に於いて唯一の神頼みであった。
さて、結局セリオが引率するアスカ達一行はセリオが加治首相に定時連絡を入れた後、明日又来ることをアルファ達に約束してから乗ってきたワンボックスカーに乗って宿へ向かった。
勿論、明日はシンジ用のチェロを携えてやって来る積もりだった。
一方、「超大型未確認機日本上空を飛行中」と言う情報をセリオから受け取った自衛隊と政府はパニックに陥った。
それはそうだろう。
何しろ、U−2やSR−71等の戦略偵察機が飛行する2〜3万メートルならばともかく、ラムジェット機の実用飛行圏とスパイ衛星などの精密映像が必要な存在がその衛星寿命と引き換えに採る超低空衛星軌道の中間という、索敵の空隙である超高空の領空侵犯は想定されていなかったのだ。
通常の対空レーダーの実用高度は「ターポン」の飛行するそれよりもかなり低く設定されていたので今まで何度か日本上空に飛来していたにも関わらず肉眼による目視で確認するまでその存在に一切気が付くことはなかったのだ。
また余りにも非常識なその実影を目にした誰もがそれを雲だと認識してしまったのもこれだけ長い間その存在が確認されなかった要因のひとつに挙げられる。
勿論、自衛隊以外にも気象庁の気象レーダーなどがあったが、前述の通り気象庁に用があるのは対流圏に存在する雲であり、雲の存在しない成層圏以上の高空は問題外だった。
静止衛星軌道上の気象衛星「ひまわり」が存在していればまだしも静止衛星軌道(地球の周回周期が二四時間で地球の自転に併走する軌道である赤道上三六〇〇〇キロ)より遠軌道は相克界という謎のフィールドによって侵入が不可能であった為ひまわりは現在の所行方不明、現在新ひまわりの打ち上げを計画している段階ではそれも叶わなかった。
アンノウンに対する航空臨検も、通常のジェット機では目標の高度(七万メートル)に上がるのも無理な上、例え上がってもその速度の前にはウサギとカメ。
宇宙ロケットはそれ以上の高々度に衛星を打ち上げるためのものであって、大気圏上層を水面に叩き付けた平たい石のように跳ねて行く航空機に並走する事など無理。
亜宇宙戦闘機や高々度迎撃機のない現在の状況では....γ号が破壊され修復作業中のウルトラホーク1号か、彼らの世界にかつて存在した国際科学警察機構(S.S.S.)で様々なミッションに使用されT.D.F.でも様々な研究母体および連絡用として購入されたジェットビートルか、その他で大気圏上層部で行うこのミッションに使用出来そうな飛行物体としてはARIELに弾道軌道ミッション用のバックパックを付ければ何とかなるような気もする、が幾らあのマッドサイエンティストでもこの短時間でどうにかすることは無理だったようだ。