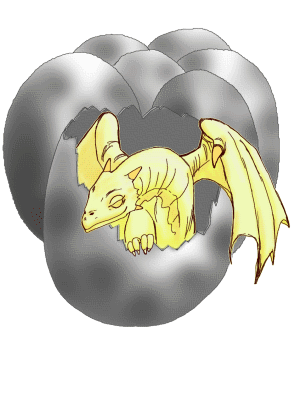スーパーSF大戦/第10話
「若者と火蜥蜴と乙女たち」」
吉祥寺に遠出してから1週間が過ぎようとしていた。
学校の授業も終わり3人はカモメ第1中学校から帰途についていた。
今日は文化祭の準備の為のホームルームが長引き、下校時刻は午後6時を回っていた。
現在3人は隣り合っている3部屋のワンルームマンションをあてがわれていた。
当然のことながら寝起きは別々の部屋なのだが、食事やテレビは真ん中のシンジの部屋でとられることが多かった。
もちろん食事の準備も部屋の片づけもシンジが行っていたのだが。
今日の夕飯の予定は野菜炒めとサンマの塩焼き用の野菜と秋刀魚、それと買い置きのための挽肉とバラ肉のブロック、その他菓子類がシンジの下げているビニール袋の中に入っていた。
彼らは夕焼けが包む海岸通りを部屋に向かって歩いていた。
シンジが重そうに荷物を運んでいる後ろからアスカとレイがてくてくと付いてきていた。
「シンジィ〜。もっと早く歩けないの? まったく。頼りがいがない」
「そんなこと言ったって、チェッしょうがないだろう。そんな事言うなら手伝ってくれればいいのに」
「だ〜め。食事当番はシンジなんだから責任もってやんなさい」
「まったく仕方ないなあ」
シンジは文句を言いながらも家路を急いだ。
運命が動き始めたのは3人が岸壁の角地の近くを通りかかった時のことだった。
レイは何となしに海の方を見ていたのだが、先の方の渚で何やらキラキラした物が動いているのに気がついた。
普段なら気が付いても無視するのが彼女のパターンであったが、この時は何故か妙に心を引かれたのだ。その為、彼女にしては珍しい行動に出た。
「シンジ君、ちょっと良い?」
「え、どうしたのレイ」
「あっちの方に何か見えたの。行ってみて良い?」
「あっちの方って、テトラポッドの間の砂浜?」
「ええ、そこで何か動いたような気がして」
「気になるの?」
「レイって、意外と子供じみてるのね」
「アスカ、良いじゃないか別に。3人で行って見ようよ。ここに越してきてから海の近くに住んでいるのに一回も海に来てないんだし」
「ああ、そう言えばそうね。うん、行ってみようかレイ」
「ありがとうアスカ、シンジ君」
人工島であるGアイランドの周辺を囲んでいる岸壁は全面コンクリートで作られているが、その8角形の各辺には市民憩いの場として人工渚が作られていた。
黄昏がすべての物を黄金色に染めている中、3人は岸壁から下にのびている階段を降りて渚の方へ歩いていった。
流木や色々な物が流れ着いている海岸は今日が大潮であることもあり、砂浜の上の方まで波を被っていた。
3人は両側をテトラポッドに挟まれた狭い砂浜の真ん中に立ち、その光景を眺めた。
彼らの眼前には、対岸に立つ建物から海に浮かぶタンカーまでそのすべての物が黄金色に染まった幻想的な光景が広がっていた。
その一瞬の光景はやがて沈み行く夕陽と共に静寂の蒼に取って代わって行き、見る見るうちに夜の帳が落ちようとしていた。
「ふう、レイにしちゃなかなかシャレた催しだったわね。感動しちゃった。ね、シンジ」
「うん、なかなか見られない風景だったねレイ」
シンジはレイに素晴らしい物を見せて貰ったお礼を述べたが、レイは相変わらず砂浜の方を凝視していた。
「どうしたの?」
「何かいる」
「何かって何? レイ」
「こっち」
彼女は砂浜の上を海の方に向かって歩いた。
「気をつけて、間違えたら波にさらわれちゃうよ」
シンジが声を掛けるが彼女は気に掛けた様子もなく波打ち際まで歩いた。
波際でキョロキョロと辺りを見回していたが、ふと、自分の足下に何かあるのに気付いた。
しゃがみ込んでみると、波によって形が崩されていたが、椀の形に盛られた砂の巣が2つあり、その真ん中に保護色を施された4〜5個の比較的大きなタマゴが砂に半分埋もれていた。
先ほどから更に水位を増した波によって水に洗われ始めており、このまま放っておけば間違いなく水に浸かってしまうだろう。
レイが触れてみると、そのタマゴはまだ暖かく、殻は固くなっていた。
「そう、まだ生きてるのね。良かった」
「どうしたの、レイ」
突然しゃがみ込んだレイを心配してシンジが後ろから声を掛けた。
そのままのぞき込んでみるとレイの足元のタマゴが見えた。
「何そのタマゴ、海亀のかな?」
「分からない、けど、このままじゃ駄目、死んじゃう」
「でも、野生の物だし、人間が触っちゃまずいよ」
「でも・・・」
「ちょっとシンジ! 何馬鹿なこと言ってんのよ。早く拾って乾かさなきゃ」
「でも野生の動物に軽々しく触っちゃいけないよ」
「そうよ、勿論。その動物の生活を脅かすような真似は絶対にしちゃいけないわ」
「だったら、分かるだろう」
「原則としてはそうだわ。でもね、このままでは確実に消え去ってしまう命を前にしてそれを放っておくなんて事、出来る訳ないでしょ」
「それはそうだけど。これが自然な事なのかも」
「アンタバカァ! これは鳥類もしくは爬虫類の卵よ、そして、世界中探したって水の中で孵化する固い殻の卵はないの、この形状からして海亀って事はないだろうけど、もしそうなら無事孵ってから海に放せば済む事じゃない。グズグズしている暇はないのよ。分かったら手伝って」
「うん、分かった」
「第一、自然動物がどれだけ貴重な物か分かってないのよ。有史以前から人間が滅ぼしてきた動物は無数に存在するけど、もう既に人間が保護しなくちゃ絶滅する生物の方が多いんだから、自然に任せて生態系を回復させるなんてセリフは六百年前に言ったって遅すぎるんだからね、そこら辺を自覚しなきゃダメよ」
「そうなんだ、自然に放っておくのが一番良いって思ってた」
シンジの素直な意見にアスカは鼻で笑ってから答えた。
「この地球上の何処にそんな場所が有るって云うのよ、なければ人工的に作り出すしかないわよね、そしてその中で生活する生物は生存本能をなくさない程度に保護するのが唯一の知的生命体である人間の義務な訳よ」
アスカはセカンドインパクトによって壊滅した環境によって生み出され、一般化していた自然保護論をシンジに語っている間にも濡れた砂に埋まっている卵を掘り出し、殻を割らないように注意しながら一カ所に集めていた。
その一方でこの2つの巣の他に卵の入った巣がないかを注意深く確認してみたが、その2つの巣以外にはただの砂浜が広がっているだけであった。
「さて、問題はこの卵をどうするかよね」
「えっ、ここに埋めて行くんじゃないの?」
「それが出来れば・・・、私の記憶ではこの地域でこのような場所にこの時期にこのような巣を作って卵を生む生物をしらないわ。つまり、この時空融合で紛れ込んだ迷鳥のような物の卵だと思うの。だからこのまま砂に埋めていても多分・・・」
「死ぬの?」
「ええ、私の知識ではね。でも私だって生物を飼った事なんてペンペン位しかないんだから、多分育てられない、卵から孵ったら即刻自然に帰すことになるけど、このまま見捨てるよりはましだわ」
「そうだね、卵から孵ったらすぐ帰すだけだったら出来そうだし、連れて帰ろうか、レイもそれで良い?」
「ええ、何故だか分からないけど、守りたいの、このコ達のこと」
レイが砂の上に置かれた卵たちを愛おしげに撫でた。
「それじゃ、家に持って帰ることに決定ね。シンジ、何か卵を包む物ないの」
「えっと、そう言われてもなぁ。あ、そうだ、さっき商店街のおばちゃんに貰ったこれが」
シンジはズボンのポケットから畳んだビニールの風呂敷を取り出し砂浜に広げた。
「これでどうかな?」
「そうねぇ、わたしのハンカチをパッキング材にすればなんとか割らずに済みそうね。じゃあ、これで行きましょう」
そう言うとアスカはスカートのポケットからハンカチを取り出し、上手く卵を包みこんだ。
「レイ、これ、持っていってくれる」
「分かったわ」
レイは恐る恐る手を伸ばし、風呂敷包みを慎重にしっかりと握りしめた。
「そうそう、手厚く慎重にね」
「ええ」
彼女は頷くともうすっかりと暗くなった海岸を岸壁の階段の方へと戻っていった。
「レイ、足元に気をつけてね、転んだら一巻のお終いなんだから」
「分かってるわ」
階段までの地面には潮によって打ち寄せられたゴミが溜まっていて決して容易に歩ける状態ではなかったのだが、レイはスタスタと元来た道を歩いていった。
却ってシンジの方が躓いて足を捻ってしまったほどだ。
彼らが宿泊しているアパートには7時過ぎに着いた。
3人はドヤドヤとシンジの部屋に上がった。食事と休憩は共同で行う、それが最も効率が良いからと云うのがアスカの弁であったが、実際それが一番楽だろうし、独りだけで過ごすなんて寂しすぎるとシンジも考えたので反対意見はなかった。
シンジは部屋にはいると、この前の買い物の時に空いた空箱に電気懐炉を入れ、タオルを引き、箱の中が適当な温度になるよう調節し簡単な孵卵器を作った。
アスカは自室に引かれているインターネットの情報を参照にしながら自分の知識をフル回転させて卵の孵化までの世話の仕方を考えた。
その結果、日に3〜4回ほど卵を3分の1づつ回転させれば良いだろうと思われた。
孵卵器はシンジの部屋の電話の横に置かれることになった。
卵が孵化するまでの間の世話は一応交代とされていた。
いつもだったら以前の葛城亭の様に結局シンジひとりが世話をすることになる筈だったのだが。
意外にもいつもだったら読書をしているか呆っとしているレイが暇があれば卵を見つめていて、アスカが決めた時刻になるとウキウキしたような顔をして嬉しそうに卵に触っていた。
その為、シンジが卵の世話をするのは深夜眠る直前の一回だけで済んでしまった。アスカに至っては1日に一回も触らないことはザラであった。
そして卵の殻は日に日に固くなっていった。
さて、そうこうする内にレイが卵を拾ってから1週間が経った。
金曜日、2連休の前日のその日もシンジ達は1週間分の食料品を買い込んでから帰宅していた。
夜になり、レイが卵を回そうとした手を伸ばした所、すっかり固くなっていた卵からパキパキと云う音が聞こえて来る。
レイは今までにない反応に戸惑い、食器の片づけをしていたシンジに駆け寄った。
「シンジ君・・・」
「えっ、何、レイ、どうかした?」
「卵がヘンなの」
「本当!?」
シンジはてっきり結局卵は孵らずに死んでしまったのかと早合点してしまった。
レイに急かされて卵の所へ行ったシンジは、その様子を見て慌てた。
今にも卵の内側から、ヒナが出てきそうな音を立てている事に気付いたからだ。
だが、どうして良いか分からないのはシンジもレイと同様であった為、慌てて声を上げた。
「アスカ、アスカァ! ちょっと来てよ!」
すると居間でテレビを見ていたアスカが不機嫌そうな顔を作って出てきた。
「なによぉ、今ちょうど良いところだったんだからぁ。『大佐、いけない!』『アルテイシアか?!』『シャアァァ』『チィィッ!』『大佐!』ドゴーンっ!て一番燃えるって、どうかしたの?」
普段だったらアスカの文句に平謝りするはずのシンジが台所で右往左往しているのを見てアスカは不思議そうな顔をしていた。
「アスカ、アスカ、こっち来てよ」
「だから、いったい何がどうしたって云うのよ」
「タマゴが孵りそうなんだ」
「あらまぁ、そうなんだ」
「なに落ち着いてるんだよアスカ、ど、ど、ど、どうすればいいのさ」
「落ち着きなさいって、ヒナが孵ったって特にすることは無いわよ。そうねぇ、稗と粟の配合飼料は買って有るんでしょう、その準備でもしていたら? まぁ鳥類だったらだけどね」
「あっ、そうだった。じゃあ準備しとくよ」
「そんなに慌てなくたって良いのに。シンジの子供が産まれるときもこんな感じだったりしてねぇ、まぁ私には見えないんだろうけどぉ。レイ、その時はしっかりシンジの様子を教えてよね」
アスカはクスクスと笑うと簡易孵卵器の前でどうしたらいいのか分からずに座り込んでいるレイの方へと歩み寄った。
孵卵器の中のタマゴを見てみると、確かにコツコツと卵の殻を内側から叩く音が聞こえてきた。
しかもその音はほとんど全部のタマゴの中から聞こえてきていた。
「へえ、これは壮観ねぇ。でも一斉に孵る生物って云ったら何かしら、もしかして爬虫類だったりして」
その時はアスカも、何が孵るかその正体を正確に推測してはいなかったのだ。
その正体を知ったときアスカは驚愕することになる。
アスカは電気懐炉の電源を切り、孵卵器を電話の横から居間へと持ってきた。
その横ではレイが卵が孵るのを今か今かと待ちかまえていたし、シンジはシンジで乳鉢に入れた稗やら粟を磨りつぶしていた。
「さて、シンジにレイ、何が孵るにしても独り立ちできる状態になったら自然に帰すんだからね。そこの所をしっかり自覚してから世話するのよ。分かったわね」
ふたりはいっせいにコクコクと頷いた。
うむむ、シンジとユニゾンして良いのは私だけなのに、シンジのバカァ。
内心で憤慨するアスカだったが、その時、一番大きなタマゴの殻に穴が開いたため、そちらの方に注意が行った。
「さぁて、どんな仔が出てくるのかなぁ」
アスカはとぼけた雰囲気で言ってみたが実際の所、3人ともヒビの入ったそのタマゴの様子に集中していた。
パリパリと音を立てて卵の殻に開いた穴は少しづつ大きくなって行き、中から出てこようともがいている生き物の声が漏れてきた。
タマゴに入ったヒビがタマゴの直径の三分の一ほどに広がったとき、中から金色に光った肌をしたトカゲが顔をヒョコっと出した。
もちろん、アスカもレイも爬虫類であると云う女の子らしい軟弱な理由でビックリするような心の持ち主ではなかったので平静にそれを観察していた。
ある程度顔を出した金色のトカゲは顔をフルフルと振るわせると一気に殻から身体を抜き出し、背中にあったコウモリのような羽根を大きく広げた。
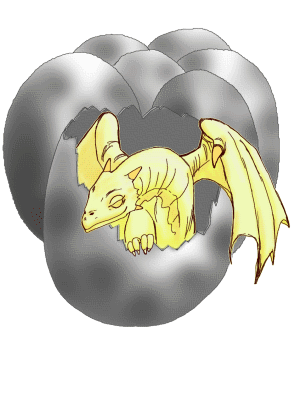
「は、羽根ぇーっ!!!」
アスカはビックリしたのを隠そうともせずに大声を上げた。
「どうしたのアスカ」
「だってだって、羽根が生えてるのよ! 前脚と後ろ脚の間に! これがどう云うことか分からないの!?」
「どう云うこと?」
「地球上の脊椎動物には2対の脚しか存在しないはずなのよ、なのにこのトカゲには3対もあるのよ」
「うん、そうだね」
「ああ、もう。そうだねじゃないでしょ」
「だってアスカ言っていたじゃない。この世界の生き物じゃないかも知れないって」
「ムッ! 確かにそうだったけど。ええ、そうだったわね。でも慌てるのに十分な理由だと思うけど」
「うん、アスカがボクには理解できないレベルの問題で驚くのは当然だよ」
「そう思うなら、」早くアナタもそのレベルまで来て欲しい物だわ。
「でもこのトカゲってドラゴンにそっくりだね」
「ドラゴン、確かにそうだわ」
キリスト教文化圏の者にとっては神と敵対する忌むべき存在のことも指す。
ドイツで教育を受けたアスカにも、その影響が確かに有ったことは確かの様だ。
その姿を見た瞬間から無意識のうちにこの小さな生物に対し、無意味な防衛心を持っていたことを彼女も認めた。−−たかが、ドラゴンに似ているだけの無垢な生物なのにね−−
それに比べて龍=ドラゴンに対して畏敬の念をもつ文化圏に育ったシンジの反応が異なったのは当然のことである。
「あっ!」 卵たちの事をずっと見ていたレイが声を出した。
いままで揺れているばかりだった残りの卵の殻も次々に破れ、中から手のひらに乗るくらいに小さい黄金色、青銅色、褐色、蒼、緑色の羽根を持つトカゲが誕生した。
それらは虹色に光る光彩をグルグルと回すと一斉に羽根を広げ、甲高い声を出しながら部屋の中を飛び回った。
部屋の扉は閉ざされていた上に当たり構わず飛び回ったため部屋のあちこちにトカゲたちがぶつかってしまった。
シンジ達はその様子をぼう然と見ていたが、2〜3分もした頃、疲れてしまったトカゲたちの動きが緩慢になってきた。
アスカ達はようやく目で追えるスピードになったためそれらを見ていたのだが、それぞれが何匹かのトカゲと目が合った。
「ダメッ! ATフィールドが浸食される?!」
レイが意外な言葉を叫ぶと同時に、3人にとてつもない飢餓感が襲いかかってきた。
レイ達は腹を抱えるとその場にうずくまってしまった。
「な、なにコレ。お腹が、空いたーっ」
「そんな、さっき夕飯食べたばかりなのに」
「・・・・・・・・・そう、この子達がお腹を空かしてるんだわ」
「え、それなら」
シンジはさっきまで熱心にすりつぶしていた稗と粟の配合飼料を差し出したがまるっきり無視された。
「ダメよシンジ、多分、この生き物は肉食だわ、冷蔵庫に行って何か取ってきて」
「分かった!」
シンジは普段見せたことのない機敏な動作で冷蔵庫まで走って行き、冷蔵庫からハムやチーズ、料理用に買って置いたバラ肉のジャンボパックを取り出すと居間に駆け戻った。
「持ってきたよ!」
シンジが肉を取り出すと文字通りトカゲたちの目の色が変わった。
シンジの手に掴まれた生肉にありつこうと、先を争うようにシンジの腕にとりつき長いしっぽをシンジの腕に巻き付けた。
その様子を見てやばいと感じたアスカはレイに指示して、シンジが持ってきた他の食物の封を切りトカゲたちに差し出した。
すると、それぞれに3匹ずつのトカゲたちが取り付き、食物を掴み出したと同時に長い首を伸ばして彼らが差し出す食物に食らい付いた。
「ホラホラ、慌てなくても十分あるんだから、もっと落ち着いてよ」
アスカはそのトカゲたちをなじりながらも器用に素早く3匹に分け与えた。
「慌てないで」レイも言葉は少ないながらトカゲたちに声を掛けながら食物、生肉は気味が悪くて掴めなかったためチーズやハムなどの加工食品を与えた。
シンジもガツガツと野生の本能丸出しで肉を食らうトカゲたちにはんばビビっていたが、目を赤く輝かせグルグル回しているトカゲたちの姿を見ていると彼らを突き動かしている飢餓感がシンジにも伝わり、夢中で手に持っている肉を口に放り込んでいった。
1週間分として買ってあった肉類の内の約半分ほどがトカゲたちの胃袋の中に消えた頃にはトカゲたちの腹はパンパンに膨れ上がり、満腹感が眠気を呼んだのか次第にウトウトし始めた。
シンジ達はさっきまでの空腹感が無くなると同時に非常に満ち足りた感覚が心を満たしていくのを感じていた。
「なに、この感覚、なにか不思議な満足感が心の底から沸き上がってくる感じがするわ」
アスカは今まで感じたこともない様な幸福な感覚が沸き上がってくるのを感じ、未体験の感覚に戸惑っていたが、トカゲたちの無防備な姿を見ていると自然に笑みが浮かんで来た。
「私も感じるわ。この子達と、凄い共感を。こんな感じは初めて」
レイも自分の腕に尻尾を巻き付けて船を漕いでいるトカゲたちに優しい眼差しを向けていた。
「うん、ぼくも何か感じてる。心が通じてしまったって感じなのかな、この小さなドラゴンたちの幸せそうにしている感覚がそのまま伝わって来る感じがする。」
シンジは彼にまとわりついているトカゲたちの頭を一匹一匹撫でていた。
「本当、かわいい子たち。私のリトルドラゴン」
アスカも普段は見せない優しい表情でトカゲたちをなで続けた。
するとその内、トカゲたちの満腹感か睡眠に誘われたのか、3人ともシンジの部屋の居間に幸せそうな顔をしてゴロンと横になり、そのまま眠ってしまった。
翌朝。・6時25分・
普段から朝食の準備などで朝が早いシンジは、胸の上に何か熱い物が乗っている事に気が付き目を覚ました。
まだ、ぼんやりとしている目でそこを見てみると昨日の晩に孵ったばかりの羽根の生えたトカゲ3匹が細い腕から生えた鈎爪をシャツにしっかりと食い込ませて眠っていた。
シンジがそれを見ているとトカゲたちも目を覚ましたのか、薄い瞼を開き、緑色に光る目をくるっと回した。
シンジはその愛嬌がある表情にクスッと笑ってしまった。
「そうか、昨日のは夢じゃなかったんだ。さて、朝食の準備・・・って、今日は学校は休みだっけ。まぁ、いいか準備をするのはアスカとレイが起きてきてからで」
ふぁぁっと欠伸をすると彼は上半身を起きあがらせようとしたが、腕が重くて持ち上がらなかった。
まだ完全に目が覚めていないシンジはボーっとしたまま右腕の方を見た瞬間、驚きで一瞬の内に目が覚めた。
慌てて左腕の方を見てみると、右腕のレイと同じようにアスカがしっかりと胸にシンジの腕を抱え込んで眠っていた。
−−どっしぇえええーっ!
−−う、嬉しい・・・じゃなくて、まずいってこれは! レイはともかく今アスカが目を覚ましたら、(想像中)、間違いなく滅殺!!
−−はっ、まずい、こんな時に、落ち着け、しかし、あ、あ、熱いリビドーが、青春のたぎりがぁ
シンジは全身から脂汗を流し緊張していた。例えしがみついていたのが彼女たちからの方であっても、彼女たちがシンジの言葉を聞き入れ、大人しく納得してくれる確率は99.9999999%あり得ない。
かならず、それと見合った報復を受けることになっちゃうんだ、彼は心の中で確信した。
−−だけど、どうにかして腕を抜かないと、どうにもならないじゃないかぁ!
シンジは心の中で絶望の叫びをあげた。
彼は何とか彼女たちが目覚める前に腕を抜き出そうと、そうっと腕を動かしたが、レイもアスカも不機嫌そうな唸り声を漏らすと「動くんじゃない!」とばかりに腕にしがみついてきた。
トホホーっとなるシンジはニヤつきそうになる頬を無理に真顔に戻すと一言呟いた。「どうしよう」と、
そんなシンジの百面相を面白そうに見ていたトカゲたちだったが、その中でも一番精悍に見える青銅色のトカゲが両脇のアスカとレイの腕にしがみついている3匹ずつの内の金色のトカゲに口笛を吹いたような高い声域の声を掛けた。
すると、それまで彼らがしがみついていた腕の主と同じようにグッスリと眠っていた金色のトカゲがパチッと目を開き青銅色のトカゲの方を向いた。
青銅色のトカゲは2匹の金色のトカゲに懇願するような調子で鳴き声を上げた。
するとアスカとレイの腕にしがみついているそれぞれのトカゲが分かったとばかりに頷いたのを見てシンジはぼう然としてしまった。
−−まるで話をしているみたいだ。はは、まさかね。
それぞれ金色のトカゲは、そんなシンジの内心を見透かしたかのような警告の声をシンジに浴びせた。
−−まさか、でも、分からないよな。未知の生命体だし。
シンジが唾を飲むと、フンとばかりに鼻息を吐いたトカゲたちは目の色を青から赤紫色に変えてグルグルと目を回しだした。
するとアスカとレイは不機嫌そうな顔をしたかと思うとしっかりと掴んでいたシンジの腕をゆっくりと離した。
シンジはその隙にと上半身を起こした。
ふたりの束縛の腕からシンジが解放されると青銅のトカゲが両方の金色のトカゲに感謝の声を上げた。
アスカの金色は得意そうに、レイの金色は無関心そうにそれに答えるとそれぞれの主人と同じようにまたもや睡眠に戻った。
シンジはこの一連のやりとりに考えるところがあったが、自分一人で結論を出しても意味がないように思えたので考えるのを止めた。
とりあえず自分の肩に止まっている青銅に感謝を込めて頭を撫でて上げた。
「ありがとう、エース。うん、お前の名前はエースがいいや」
すると残りの2匹も物欲しそうにシンジの顔を覗き込んだ。
「ふふ、ハイハイ分かってるよ。じゃあお前はブルー、お前は、えーっとタマにしよう」
シンジは自分に懐いている3匹それぞれに名前を付けた。
青銅色にはエース、蒼にはブルー、緑色にはタマ、性別すらハッキリしていない彼らに似合っているのかいないのかいまいち分からないが、タマはないのでは無いかと思う。
シンジは3匹を肩に乗せると立ち上がり自分の寝室へ行った。
そこから毛布を取ってくるとトカゲたちの邪魔にならないように、アスカとレイの上にその毛布を被せた。
ぐっすりと眠っているふたりの寝顔を見ている内に、何やら先ほどの両腕の感触が甦ってきた。
思わずニヤけてしまうシンジであったが、彼のトカゲたちがどことなく冷たい視線を浴びせているような気がした為気恥ずかしくなったのか、ムリに真顔になると台所に行き、朝食の準備を始めた。
シンジが朝食のベーコンエッグとトースト用のカスタードを作っている間、シンジのトカゲ3匹は大人しくそれを見ていた。
そして、台所から小麦粉の焼けるいい匂いが部屋を満たした頃、居間からアスカとレイが目を覚まして来た。
二人とも起き抜けでボーっとした表情で台所の方へやって来た。
「あ、シンジ、オハヨー」
「シンジくんおはよう」
「あ、ふたりとも起きたんだ。おはよう、もうすぐで朝ご飯出来るけど、どうする?」
「うん。タベルわ」
「わたしも」
「分かった、席についてて待っててね」
シンジがニコッと笑うと半分夢の世界にいたふたりはニヤーッと笑いを浮かべつついつもの席に座った。
朝食はいつもふた通りの物が用意されていた。
もちろん、肉類が受け付けられないレイと、肉類中心の献立が好きなアスカの双方の為である。
基本的に朝食はトースト・プラス一品、そして飲み物である。
今日の献立はトーストとイチゴジャム、玉子・牛乳・砂糖に片栗粉で作ったカスタードとアスカ、シンジ用にベーコンエッグ、レイ用には果物とヨーグルトが用意されていた。
奇特なことに世の中には、自ら食べられる事を望む食材もあると言う事だ。
シンジが彼女たちの前に出来立ての料理を並べると、急速に膨らむ食欲に誘惑された彼女たちは一心不乱にそれらを口に運んだ。
いつもと違う2人の様子にシンジもビックリした顔で見ていたが、彼もまたいつも以上の食欲に突き動かされトーストに手を付けた。
5分後、アスカが鍋の中にあった暖かいカスタードをトーストですくい取るようにして残さず食べてしまうとシンジの用意した朝食は全て食べられてしまった。
「ふえーっ、全部食べちゃった」
「ごちそうさまシンジ、でもまだなんか物足りないのよねー」
「ええ、まだ足りない気がする」
「あっ、そうだった」
シンジは食卓から台所へ行ったかと思うと、湯がいた豚肉が入った大きめのボールを持ってくると食卓の上に置いた。
「残っている肉って豚肉しかなかったから煮て置いたんだ。生で食べると寄生虫が怖いからね」
そう言いながら彼は肉片を三つ摘むとひとつを肩に座っている青銅のトカゲに差し出した。
彼はシンジに向かいクゥンと確認するような鳴き声を上げた。
「お食べ、エース。ブルーとタマもこっちへ」
シンジが呼びかけるとテレビの上で物欲しそうに丸くなっていた蒼と緑のトカゲが翼を広げて宙を飛び、シンジの腕や肩にしがみついてきた。
「ほらほら、慌てないで」
アスカとレイはシンジを無言で見ていたが、その内アスカが口を開いた。
「なぁに、シンジ。もう名前付けちゃったわけ?」
「え、う、うん。まずかったかな」
「だって、自然に帰すって約束だったでしょ。後がつらいわよ」
「そうだけど。本当に自然に帰せるのかなぁ。これって普通の生物じゃないし、しっかり結びついちゃってる様な気がするんだけど。アスカ、イヤなの」
「そんな訳」
アスカはジッと自分を見つめる黄金のトカゲに視線を向けた。
その黄金のトカゲから投げかけられる情愛の念は彼女にとっても魅力的で有りすぎた。
しばし自然保護の観念とか希少動物の価値等の社会的通念と自分が望む物との間に激しい葛藤が行われたが、結局3匹のトカゲたちの愛らしい魅力には勝てずあっさり屈服した。
「そんな訳無いじゃない。・・・・・・レイあなたは・・・」
アスカはレイの意見を聞こうと彼女の方を見たのだが、そこにはごく自然な笑顔を浮かべて肉を手づかみで自分のトカゲたちに与えるレイの姿があった。
菜食主義を貫いていたレイが見せた意外な光景にアスカは口をつぐんだ。
「あ、あのレイ、大丈夫なの?」
「何が?」
「だってアナタ、肉は気持ち悪いからって見るのも嫌がっていたじゃない」
「ええ、そうね。だって生き物を殺してその肉を喰らうだなんて、とてつもない罪悪だと思っていたの。そこまでして生きる必要があるのかって、でも」
そこまで云うと一瞬痛々しい表情を浮かべた。だが、その後に見せた表情は非常に印象に残る物だった。
「でも、それはとても自然なことだったのね」
アスカは鉄のボールから肉を摘み、傍らで催促している3匹のトカゲ、金色褐色緑色に与えていた。
彼女は自分が与えている肉片をトカゲたちが貪り食う様子を見ながらレイに訊いた。
「レイ、アナタはその子達の名前、考えた?」
「いいえ、まだ考えてないわ」
「フフ、ワタシは考えたわよ。金色のこの子はブロンディー(金髪美人)、褐色の子はカッパー、そして緑色の子はブルネット。ね、良い名前でしょ?」
「ええ、そうね。でもブルネットって黒髪の事じゃ無かったの?」
「ふふん、日本語の形容詞にこういうのがあるわ、碧の黒髪って、知らないのー?」
「その言葉は知ってるわ。でも、そう・・・そう決めたならワタシが反対する理由はないわ」
「でさ、レイの子達の名前はどうするのよ。名前くらいつけてあげなきゃ可哀想だわ、私たちの家族なんだからサ」
「そうね」名前、個体を識別するための記号に過ぎなかった物。でも、それだけじゃないのね。
「私は、・・・」
しばしの間、レイは考え込んだ。
今まで自分の物を持つと云う経験すらなかった彼女に、名前をつけると言うことは他人が考える以上の労力を強いることであった。
だが、彼女には同じ竜の子を持つ仲間がいた。
彼女はそれを参考に、自分が感じたままに名を付けていった。
「この子はゴールディ、この子はアオ、この子はミドリ」
「ふぅん、なんのひねりもないジャン。それで良いの?」
「ええ、これがいいの」
アスカは少し気に入らない様子だったがレイは気にしなかった。
「ま、いいわ。でも本当、可愛いの! いいコいいコ」
アスカが手のひらサイズのブロンディの頭を指で擦り付けるとブロンディは光彩を緑色に光らせ、目玉をグルグルと回して上機嫌を表現した。
そこに洗い物を済ませたシンジが台所から現れた。水色のエプロンがお姉さま方の人気の秘密である。
彼の肩には颯爽とした感じの青銅のトカゲ・エースが辺りを見渡していた。
それはまるで自分が見張りをしていると言った感じに見えた。
タマは机の上で丸くなっていたし、ブルーは文字通りブルーな少し前までのシンジそのものの感じでシンジの左腕にしがみついていた。
「今日の予定だけどさ」
彼がふたりに声を掛けると彼女たちはシンジに注目した。
「ど、どうしたの?」
「バカねぇ、なにビビッてるのよ。」
「それで、どうしたの」
レイが促すと、シンジは続けた。
「あ、うん。今日午後からGGGでシンクロテストだけどさ、それまで何か予定があるのかなぁって思って」
「ああ、そう言えばそうだっけ。特にないけど、どうして?」
「いや、特にないならいいんだけど、部屋の片づけとかやって置こうかなって思ってたからさ。洗濯とか」
ふぅ〜ん。
「ホント、シンジってマメねぇ。少し位散らかったって死にはしないのに」
そう言う風に言ったアスカにシンジは呆れた。
「アスカ最近」「ミサトに似てきたねぇ、なんて言ったら! どうなるか分かってるわよね」
アスカはシンジが言いかけたセリフを途中で奪い取り、シンジの口をふさいだ。
まさに図星だったシンジは、アスカの笑顔に秘められた怒りに恐れをなして口をつぐんでしまった。
−−気にしてるんだったら直せばいいのに。
「あらぁ、どうしたの、シンジ。」
「ア、アスカ朝シャンはしないの? 今日は」
「わざわざ、私の衛生状態にまで気を使っていただいてアリガト。でも、そういえば昨日はお風呂に入ってないのよね、アタシ部屋に戻ってお風呂に入ってくるワ」
「あ、ワタシも、赤木博士に衛生状態を保つように言われてるから」
そう言うとふたりは連れだってそれぞれの部屋に戻っていった。
「ふう、やれやれ、バクダン踏むところだったよ」
「そうそうシンジ!」
部屋に戻ったはずのアスカが又扉を開けてシンジの部屋の中に顔を入れた。
「うわっ! っとアスカか」
「どうしたのよ」
「いや、一寸不意を突かれたから、」
「ふぅん。チョット買い物頼みたいんだけど、いい?」
「いいけど、何?」
「うーん、実はね、この子達の食事なんだけど、普通の赤身の肉ばかりじゃ栄養が偏っちゃうのよねぇ。だからさ、ペットショップに行ってコオロギとか買ってきてくれない?」
「コオロギ?」
「そうよ、やっぱり生き餌とか必要じゃない? 多分ペットショップの人に訊いても分からないと思うのよねぇ。第一、なんて説明して良いのか」
「どうして? 向こうはペットのプロじゃん」
「だって、恒温の爬虫類なんてアタシ知らないわよ。強いて言えば鳥類が一番近いけど、鳥に見える?」
「見えないけど」
「でしょ?」
それじゃあ頼むわね、アスカはそう言うと今度こそ本当に自分の部屋に戻っていった。
シンジも部屋の片づけは後回しにして、近くの街へと出かけていった。
午後になってGGGへ向かおうとした時、ちょっとしたトラブルが発生した。
この生まれたばかりのトカゲたちをどうするか、結局の所シンジの部屋にエサを用意し全員置いて行くことにしたのだがレイが最後までグズっていたため出発時間が五分ほど遅れてしまった。
なにしろ、このような生物を連れて行き町中で騒ぎになったら大変である。
また、GGGのメンバーに知れたりしたら研究材料として没収されてしまう可能性だってあるのだ。
その日に行われたGGGでのエヴァンゲリオン起動実験は何のトラブルもなく終了した。
もともと、GGGの製造した兵器ではない為、エヴァンゲリオンの整備、補修、使用は調査されたコンピューターや構造から類推された情報を元に手探りの状態で行われていた。
シンクロテストが終了し、エントリープラグから出てきた彼らはヘルメットをつけたままシャワーを浴び、代用LCLを入念に落としてから更衣室へ向かった。
この世界へエヴァ3機だけで来てしまった関係から、様々な物が足りなくなったエヴァンゲリオンであったが、特に問題となったのがエヴァのパイロットの衝撃緩衝材であり、シンクロ率を高める働きと生命維持を図るLCLであった。
再生が効くとはいえ、その絶対量が少なかったLCLはGGGの実験の最中に枯渇してしまった為、衝撃緩衝材としての役割だけを求めた代用LCLによってエントリープラグを満たす方法を採る事となったのだ。
だが、そのためにパイロットの呼吸はヘルメットを被り管によって補給する方法へと変更されていたのだった。
幸い、プラグスーツはそのまま使用、再生産できたためヘルメットの新設だけで済んだ。
更衣室で着替えた3人は、そのままメインオーダールームへと呼び寄せられた。
メインオーダールームではGGGのメンバーが彼ら3人を待ち受けていた。
「ヨ、お疲れさん」
Gストーンによる無限情報サーキットによってその生命を維持している獅子王凱ことサイボーグ凱が陽気な調子でシンジ達に声を掛けた。
それまでコンソールに向かって何かのオペレーションをしていたミコトは3人が入って来たことに気付くと席を立ち彼らに近寄った。
「シンジ、アスカ、レイの3人ともご苦労さま。何か飲む? ワタシ、コーヒーを入れるのには自信が有るんだ、煎れてこようか?」
3人とも頷くと、ミコトは砂糖、ミルクが必要かを質問し、そそくさと給湯室へ小走りで向かった。
「フフーン、彼女の煎れてくれるコーヒーは大変濃くて大人臭い香りがしますです。お子さまの人では大丈夫ですか?」
ムカッ
「あ〜ら、所詮アメリカンコーヒー何か飲んでる人のレベルの話でしょ。本場ドイツのコーヒーを飲みなれているアタシにはちょうど良いんじゃないかしら」
「ム、何言ってるですか。第1アナタアメリカ人でしょう。人のこと言えませんです」
「こちとらドイツ生まれのドイツ育ち、国籍以外はドイツ人みたいなものよ」
「つまり、エセアメリカンってわけですねぇ」
「何ですってぇ!」
「まぁまぁ二人とも、そんな事で言い争わないでくれたまえ」
些細なきっかけでヒートアップしたスワンとアスカの言い争いの間にGGGの長官である大河長官が割り込んだ。
「「そんな事!!?」」
ユニゾンで聞き返してきた二人に気圧された大河長官であったが、エヴァンゲリオン適格者の3人に対する重要な連絡事項があるとかなんとか、ようやく2人をなだめすかした。
不満気な表情でそっぽを向き合うふたりであったが、そこへやっとミコトが戻ってきて彼女特製の濃ーいコーヒーをご馳走した。
「子供」と莫迦にされたアスカは当然の事ながら何も入れずにブラックのままクイッと喉へ送り込んだのだが、本当に濃厚な風味に蒸せた喉のせいで意志に反してコーヒーを吹いてしまいそうになった。
だがしかし、彼女の強固な意志は体の反射行動すらも抑制し、コーヒーをゴクリと音を立てて飲み干した。
「フ、ふぅ〜ん。確かになかなかいい味じゃない。もう一杯いただくわ」
アスカはスワンに向かってニヤリと笑うとミコトにお代わりを頼んだ。
ちなみにシンジは苦み走った表情をしながらタップリとミルクと砂糖を入れたコーヒーを我慢しながら飲んでいたし、レイはミルクのみを入れた物をチビチビと飲んでいた。
やはりお子さまの敏感な味覚には少しキツイ代物であったようだ。
さて、少し時間が経って落ち着いてきた頃、アスカは大河長官に質問した。
「それで長官、私たちに連絡って何な訳?」
「ふむ、実はね君たちの身柄に関することなのだが・・・」
大河長官はそこまで言うと一度彼らの様子を見渡した。
彼らも大河長官が何か重大なことを言わんとしていることに気付き、一様に緊張を高めた。
「今までは君たちの身柄は我々GGGが保護してきたわけだが、君たちにはGGGの組織から外れて貰うことに決定した」
「ええーっ!!!」
アスカとシンジが大声で叫び声をあげた瞬間どこからともなく彼らのトカゲが現れ空中をバタバタと飛び回った。
突然現れた謎の生物にGGGのメンバーも彼らの事を隠そうとしていたアスカ達も慌ててしまいパニックになってしまった。
アスカのブロンディーとカッパー、シンジのエース、レイのミドリは長官を威嚇するように声を上げつつ彼に襲いかかる仕草を見せていた。
そのほかのトカゲたちは自分の飼い主の体に長い尻尾を巻き付かせ、飼い主を敵から守るように威嚇の声を上げていた。
「ブロンディー! カッパー! 戻って!」
「エース止めるんだ」
「ミドリ戻って」
3人が呼びかけると興奮していたトカゲたちもパタパタと翼をはためかせながらそれぞれの飼い主の体にしがみついた。
一瞬の静寂。
赤い光を宿した目をしたトカゲたちが上げる威嚇の声だけがメインオーダールームに響いていた。
「君たち、それはいったい何なのかね?」
それまで一言も発せず呆然としていたGGGのメンバーであったが、その中で最も高齢の禿頭の老人、獅子王麗雄博士が興味を引かれたのか怖ず怖ずと質問した。
何なのかねと尋ねられても彼らだってその正体を知らないのだから答えようがなかった。
「海岸に落ちていた卵から孵った子達です。恒温の爬虫類、六つの脚を持つ我々とは異なる系統の生物と言うこと以外分かりません。なにしろ昨日卵から孵ったばかりだし、それ以上のことは私たちだって知らないわ」
アスカはほとんど投げやりな態度でその質問に答えた。
「なるほど、それでは仕方ないな。しかしどうやってここに?」
「それこそ分からないわ。」
アスカはお手上げとばかりに肩をすくめた。
ふうむ、獅子王博士は唸るとトカゲたちをジロジロと眺めた。
「どうだろう、少し我々に調査させてくれないかね?」
「ダメ!」
拒絶の言葉は意外にもレイが発していた。
どうやら今朝の話しに上った〜GGGに知られたら実験動物として〜の話を思い出したらしい。
それほどまでにレイとトカゲたちとの結びつきは大きくなっていた。
いきなり拒絶の言葉を喰らった大人達は動揺を覚えたが、アスカは条件付きで調査に付き合うことに同意した。
1.トカゲたちの生命の保証をすること。
2.調査結果は私たちにも報告すること。
3.苦痛を与えるような実験はしないこと。
4.調査期間中の食費はGGGが負担すること。
5.この生物の所有権は私たちにあること。
等々、実に様々な要求を突きつけたが大河長官と獅子王博士はあっさり承認した。
「なら、問題はないわ」何にしろ科学的に調査するには設備と金が必要だもの。法の後ろ盾があるのも頼もしいことだし。「まぁ、この子達の事は後にするとして。さっきの話の続きを聞かせて貰いましょうか。どうして私たちを放り出すなんて言うのよ。まさかアタシのエヴァンゲリオンを接収するなんて言うんじゃないでしょうね」
「いや、そうではない。エヘン!」
大河長官はひとつ咳払いをするとおもむろに話し出した。
「実は今度日本政府が統合されるのに伴い、日本を防衛する為の国内の軍事力の統合・再編成が行われることになったんだ。そこで、君たちについてはそちらの新戦隊に移籍することになったのだ、勿論今すぐというわけではない、エヴァンゲリオンを整備運用するためにはそれなりの設備が必要だからね。当分はGGGの所属と言うことになる」
「ふぅん、なるほどね。それで私たちはどういう部隊に配属される予定なの?」
「それなんだが、時空融合したことによりどうやらこの世界には多数のロボット兵器が現れたらしい。そこで政府はそれらを集め陸海空に続くスーパーロボット隊を作るとの事だ」
「それって見せ物って事?」
「うん? 何故だね?」
「だって、ロボット兵器の運用には膨大な整備、物資等々の運用を妨げる要因が沢山あるわ。だとしたら砲門外交に代表される他の勢力に対する示威としての見せ物にしかならないんじゃないの?」
「うむ、確かにそれはある。しかし、局地戦等の極限の戦場での汎用性と生存性が群を抜いていることも確かだ。政府の委員会では決戦兵器としての価値があると見ていると私は見ている。それにスーパーロボット隊単独での作戦よりも他の隊との共同作戦もしくは支援活動の方がメインになると思うな。これでは不服かな?」
「ふーん、なるほどね。それなら少しは納得が行くわ」
アスカは納得した様子で大河長官の言葉に頷いた。
「で?」
「まだ何かあるのかね」
「さっきの言葉からするとGGGは参加しないみたいだけど、何故なの」
「それは、つまり、GGG憲章第3条ガッチィ・ジオイド・ガードは人類に襲いかかるあらゆる敵に対して敢然と立ち向かわなければならない。我々は決して人類を相手にその力を振るってはならないと決められているのだ。そして、この地には未だにゾンダーが潜伏してその力を振るおうと企んでいる。ギャレオンから得た情報からするとただ一つのゾンダーが成熟するだけでこの地球の生命体はすべてゾンダー胞子によってゾンダーと化してしまう、我々はゾンダーとの戦いが済むまでは奴らに対する警戒を続けなければならないんだ。分かって欲しい」
大河長官は済まなそうに顔をしかめた。一人前の大人が何かに誓い約束した事を破るというのは本来なら有ってはならないことである。しかし、それを破ってでも行わなければならない大人の事情という状況がそれを妨げることがある。
今は正にそれだった。
アスカも状況からどの様な取引が行われたかを推察し、他に手はなかったのだろうと諦めにも似た感傷を抱いた。
「決まったことなんでしょ・・・」
「済まん」
大河長官は素直に頭を下げた。
午後5時30分/メインオーダールームからの帰り道。
彼らはスワン・ホワイトが運転するランドクルーザーに乗りアパートまで送ってもらっていた。
彼らだけで有ればGアイランドに整備されている交通網を使用して帰ることもできたのだが、興奮し少しの刺激でも騒ぎ出しそうになるトカゲたちを連れてではそれはムリだった。
シンジが助手席に座り、アスカとレイは後部座席に座り、目を薄赤く光らせているトカゲたちの頭を撫でなだめていた。
彼らはクルマに中に入ってからも沈鬱な雰囲気を漂わせており、口を利いていなかった。
それは根っから陽気なヤンキー・・・アメリカ人のスワンには耐え難い物であったのだろう。彼女は出来るだけ明るい雰囲気を作ろうと口を開いた。
「そう言えばシンジ、そのドラゴンたちはドコで見つけたのですか?」
「ハイ?」
シンジは突然スワンが自分に話しかけてきたのにビックリして訊き返した。
「え、えーとですね。1週間前のことなんですが・・・」
シンジはその時のことを簡単に説明した。
スワンはそれを聞き、自分もそれを手に入れようと思い立った。
「そうですか、今行けば他の巣が見つかるかも知れないですネ」
軽く言った言葉だったがアスカはそれに簡単に答えた。
「残念でした、アタシも探してみたけどもう他にはなかったわ。それに私たちの子が孵ってるんだから、まだ他にあったとしても卵の殻しか残ってないんじゃないの?」
「ふぅ〜む、それは残念デース」
会話が終わるとまた車内は沈黙に包まれてしまった。
シンジはそんな雰囲気が気になってしまい、何かしゃべるきっかけを探していたのだが、期せずしてそのネタが見つかった。
車窓の外にちょうどあの卵を見つけた海岸が映ったのである。
「あ、スワンさん。あそこの砂浜で卵を見つけたんです」
「えっ?ドコですか?」
「あそこの一番奥のテトラポットの手前にある砂浜です。あの日は丁度黄昏時で、海がキレイだったんですよ」
そう言ってシンジが海の方に注目すると、Gアイランドの沖合に投錨している鋼鉄製の軍艦が目に入った。近代的な護衛艦とは全くシルエットが異なるハリネズミの様に武器を突きだした砲艦が1隻と、素人が見たらタンカーと思ってしまうかも知れないノッペリとした甲板を持つ航空母艦、そしてそれらの護衛として数隻の武装船とそれらに混じって近代的なアルミ製の護衛艦が数隻停泊していた。
「アレ? 何かずいぶんゴツイ軍艦が泊まってますね」
「シンジもやっぱり男の子ですネ、ちょっと止まって行きまショー」
そう言うとスワンはランドクルーザーを路肩に止めた。
スワンは何となく面倒臭そうにしているシンジとアスカ、レイをクルマから追い出すと、コンクリート岸壁の前に立った。
しかし、そこにはひとり先客がいた。
「あれ? 碇クンと惣流さんに綾波さんじゃない」
彼女はさっきから停泊している軍艦を双眼鏡で熱心にネイビーウォッチングしていたのだが、後ろから人が近づくのを感じて振り返ってみたら知り合いだったと云う訳だ。
彼女は彼らの名前を呼びながら今まで観察していた軍艦との妙な符号に気付きニンマリと笑みを浮かべた。
「あれ、初野さん」
「もう、あやめで良いって言ったじゃん」
「あ、そうだった。ははゴメン」
「ねぇねぇ、それよりもさぁあのフネ見てよ」
「ウン、なんか妙にゴツクない? あの軍艦」
「あ、分かる? そうなのよあのフネどう見ても第2次世界大戦の時の軍艦にしか見えないのよねぇ」
「WWⅡの軍艦?」
それまでやけにシンジに馴れ馴れしく話しかけるあやめに半ば嫉妬の念を抱いていたアスカがあやめの答えに驚いて声を上げてしまった。
「ええ、そうよ」
やけに確信を抱いているあやめの返事にアスカは思わずスワンに振り返る。
するとスワンは無言で頷いた。公開組織になったとはいえその構成要員まで一般に公開できるほどGGGも開けっぴろげでないため、一般人(とは言えその正体はウルトラセブンに変身に出来ると云うとても一般人とは言えないあやめでは有ったが)の前で迂闊に秘匿情報をしゃべるわけにも行かなかった。
あやめはそんなアスカの様子も気にすることなく口元に笑いを浮かべながら沖合に浮かぶ軍艦の説明を始めた。
「説明すると、沖合で「錨」を降ろしているあの一番大きなトゲトゲの軍艦は巡洋戦艦の穂高級、全長261メートル基準排水量37,515トン、主砲は50口径40センチ砲連装一基、三連装二基計八門。その横に見えるのが航空母艦の「蒼龍」、それで一番手前に停泊しているのが駆逐艦の「綾波」どれも太平洋戦争で戦っていた軍艦なのよね」
正確に言えば駆逐艦は軍艦と分類されていなかったらしいが、軍用のフネである事には違いない。
実はこのフネは呉に集結している連合艦隊から派遣され、直に行われる紅海への護衛艦隊の作戦行動に関する最後の詰めを行う為の使節団を連れて来ていたのである。
それはさて置き、目の前にいる軍艦の船名が自分たちの名前と同じであると知ったときのシンジとアスカの表情はあやめを満足させる物だった。レイの表情は今いち読み切れなかった様だが。
シンジ達が帰る段になってもあやめはまだ船を見続けていた。
よっぽど好きなんだなぁとシンジは思った。『女の子にしては珍しいシュミしてるなぁ。本当ケンスケと気が合いそうなんだけど』
帰りの車中でシンジ達はスワンから花見を兼ねた送別会が上野の公園である事を伝えた。
部屋に戻ると彼らは疲れた様子で食事を摂るとそのまま疲れたように眠ってしまった。
予告編へ
スーパーSF大戦のページへ
岡田さんのホームページにある掲示板「日本連合 連合議会」への直リンクです。
感想、ネタ等を書きこんでください。
提供/岡田”雪達磨”さん。ありがとうございます。
ご感想を下さい!